
(記事初出:韓国出版文化産業振興院Webマガジン「K-BOOK Trends」Vol.50|
インタビュー・構成:늘품플러스|翻訳:牧野美加)
世の中には自分たちの知らないさまざまな領域がある。そして多くの人は、よく知らない領域に対して偏見を持ったり、外から見える姿だけで安易に判断したりしてしまう。マジョリティーの判断によってマイノリティーの居場所が狭まっているこの時代に、「誰もが欲望することのできる時代」を夢見る人がいる。弁護士、演劇人、作家、ダンサーなど多様な姿に変化しつづけながら、欲望を現実へと変えているキム・ウォニョンさん。彼は、障害者をはじめとするマイノリティーの話に耳を傾け、その声を心から支持する。そして誰もが美しい存在であり得る世界を夢見ている。すべての人が共に生き、欲望し、自分自身としての存在が認められる社会を願いつつ、ものを書き、踊り、表現することをやめないキム・ウォニョンさんに会った。
——ウェブマガジン「K-Book Trends」に登場していただくことになり、うれしく思っています。読者へのあいさつと簡単な自己紹介をお願いします。
読者のみなさん、こんにちは。『「失格の烙印」を押された者たちのための弁論』(サゲジョル刊、小学館より邦訳刊行予定。邦題『だれも私たちに「失格の烙印」を押すことはできない』)などの本を書いたキム・ウォニョンです。弁護士として一定時間働き、それ以外の時間はもっぱら、ものを書いたり舞台づくりをしたりして過ごしています。
——弁護士や演劇人、作家という多様な分野で活動なさっています。法律や演技、文章によって「何かを表現し、代弁する」という共通点があると思うのですが、なかでも作家としての活動はご自身にとってどういう意味を持っているのでしょうか。
ある社会的立場や存在を「代弁する」という気持ちを持っていたこともありますが、今は違います。弁護士、演劇人、作家といった役割は、生計を維持するため、おもしろいから、あるいは気づいたらやっていた、といった感じの、それぞれ独立した分野です。ちょっと抽象的に聞こえるかもしれませんが、そういう役割の根底には、わたしが常に関心を寄せている「権利」と「美しさ」という二つのテーマが存在します。
とりわけ作家としての活動が一番重要だと言えます。いろいろな社会現象について考え、障害のある個人として生き、多様な本を読み、各種法律問題に直接・間接的に関わることで形成されてきた自分の問題意識や関心。それらに名前をつけ、互いに関連づけ、統合していく一番基本的な作業が「書く」ことだからです。もちろん、書くことを通して、さまざまな読者と直接会えるというのも大きな魅力です。

——『希望ではなく欲望』(プルンスプ刊、クオンより邦訳刊行予定。邦題『希望ではなく欲望——閉じ込められていた世界を飛び出す』)、『だれも私たちに「失格の烙印」を押すことはできない』、『サイボーグになる』( サゲジョル刊、岩波書店より邦訳刊行予定。邦題『サイボーグになる——テクノロジーと障害、わたしたちの不完全さについて』)などの著書で、障害者をはじめとするマイノリティーのために声を上げていらっしゃいます。本を書こうと決心する決定的なきっかけはありましたか。また、本を書くうえで一番気をつけているのはどんなことでしょう。
どの本も動機は少しずつ違います。『希望ではなく欲望』の場合、2000年代中盤に初稿を書いたのですが、当時わたしは20代半ばでした。そのころの韓国社会は今とは比較にならないくらい、わたしのような「障害のある人たちの話」に関心を示しませんでした。示すとしても、一部の「障害を克服した著名人の話」として注目したに過ぎません。もともとわたしは人から注目されたいタイプで、二十歳前後は特にそうでした。自分の経てきた固有の、あるいは不当な経験、そして驚くような瞬間、そういうことを話したいという欲望が大きかったのです。
最初に出した本の動機が自分の話を伝えたいという欲望だったとしたら、二番目の本『だれも私たちに「失格の烙印」を押すことはできない』は、自分の人生から沸き起こる重要な問いに答える、というのが動機でした。「極度の障害を抱える人にも尊厳があるとしたら、それはなぜか。ただの道徳的な模範解答ではなく、本当に尊厳ある存在であるならその根拠は何か」。そして「このルッキズム(外見至上主義)の時代に、身体的な制約や変形の激しい人も美しい存在であり得るか」。この二つの問いがありました。それらに自分なりの答えを出していく過程が『だれも私たちに「失格の烙印」を押すことはできない』です。わたしもあなたも尊厳があり、同等な権利があり、美しい存在であり得る、ということを理性的に論じてみようというものでした。
『サイボーグになる』を出したあとに書いた文章は、社会全体でぜひ考えてもらいたいテーマを広く伝えよう、というのが原点になっています。ですが、その根底に流れている自分自身の課題は常に同じです。善良な心や宗教的な信念に頼ることなしに「いかに、わたしとあなたの身体は同等な権利を持ち、美しい存在であり得るか」という問いに答える、というものです。
——『サイボーグになる』はキム・チョヨプさんとの共著です。身体障害のあるキム・ウォニョンさんと聴覚障害のあるキム・チョヨプさん、お二人で一つの話を展開していく過程はいかがでしたか。
キム・チョヨプさんは真面目で聡明な作家です。ノンフィクションでこういうテーマを扱うことにわたしは経験がありましたが、チョヨプさんは初めてでした。でもいろいろなテーマについてどんどん勉強し、互いに決めておいた期限をきちんと守って書いてくれました。おかげでわたしも刺激を受けて、いっそう熱が入りましたね。二人の具体的な作業スタイルには大きな違いはありませんでした。ただ、チョヨプさんがご自身の個人的な話にはやや慎重に触れていたのに対し、わたしは自分の経験をおおいに活用した、という点は違っていましたが。
——『サイボーグになる』の中で、科学や技術の領域がはらむ「非障害者中心主義」を懸念されていました。障害を「除去」するのではなく障害と「共に」生きていくためには、科学技術は今後どのように発展していくべきでしょうか。
非障害者中心主義とは、常に障害を除去すべき否定的なものとして捉え、画一的に規定された「正常な身体」のみに価値を置く姿勢を指します。一般的に、障害に伴う困難や苦痛は当然解消すべきものと考えられていますが、わたしはこの本で、障害とは単なる生理的な苦痛ではないことを示そうとしました。障害は、一人の人間の持っているアイデンティティーとして尊重されるべき側面もあるのです。
技術というのは、完成した結果物だけを指すのではありません。まず構想し、必要な知識を体系化し、経験的に検証し、各種テストを経て生産されたあと、さまざまな方法で宣伝され、社会に共有されていく一連の過程を指します。わたしたちはその過程全般に注目します。「障害者に必要な技術とは何か」を考えるのは誰か? 構想されたアイデアを体系化していく際、障害のある身体の経験はどのように反映されているか? 障害のある身体は検証過程に加わっているか? 加わっているならそれは誰か? 障害には膨大な種類があり、その程度も千差万別です。また、完成した技術のPRの仕方はどうか? わたしは、今を生きる障害者の生活を尊重しつつ、技術的な助けが必要な人のもとに有用な技術を効果的に届けようとする努力を支持します。
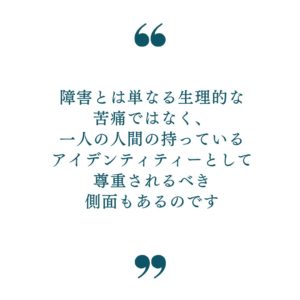
——著書の中で特に愛着のあるものはどれでしょう? その本を執筆していたときの気持ちやエピソードがあれば教えてください。
わたしは何年かに一冊のペースで本を書くタイプです。なので、どの本にもかなり力を注いでいます。最初の著書『希望ではなく欲望』は、今あらためて見ると気恥ずかしくもあるのですが、2000年代を生きる20代の自分の姿が現れているので格別な存在と言えます。当時も「あぁ、こんな文章、ただの自意識過剰じゃないか」と頭を抱えたりもしましたし、かと思えば、何日も食事も忘れて自分でも驚くほどすらすら書き進めたこともあります。まるで、ものすごく長いクラシックの曲をミスなく演奏しているような気分でした。今はもうそんなふうには絶対書けないと思うし、そうやって書いた文章は何日かして読み直してみたらめちゃくちゃだった、ということが多いです。とはいえ、もうあんなふうには書けないというのはちょっと残念でもあります。
——『希望ではなく欲望』の中に、「生きる資格のない人間などおらず、誰でも堂々と欲望を抱いていいのだ」というくだりがあります。世界的に「嫌悪の時代」とされる今、「誰でも堂々と欲望を抱くことのできる時代」のためには、どういう姿勢が必要でしょうか。
さまざまなものに閉じ込められて生きている人の場合、みずからの欲望を勇気を出して表現するだけでも充分、政治的な実践になると思います。ただ、誰かの欲望を「聞く」立場に立った場合、必要となるのは、嫌悪にせよ熱狂にせよその欲望に反応する前に、少し立ち止まってみることだと思うのです。この社会の一番大きな問題は、必要以上に素早く「反応」することに端を発しているのではないかと。嫌悪の言葉を浴びせたくなったら、立ち止まって、もっと耳を傾けてみてください。熱狂し支持するあまり、それに同意しない人を嫌悪主義者だと批判したくなる? それでも立ち止まって、もっと耳を傾けてみてください。勇気を出して欲望を語ること、誰かの欲望に対し、少し間を置いて慎重に答えること。この二つがわたしたちに必要なのではないかと考えます。
——性別や家庭環境、容姿、障害といった克服できない条件を前に、わたしたちは時に無力さを感じます。『だれも私たちに「失格の烙印」を押すことはできない』は、自分自身を受け入れられない人たちのことを「法律」という公的な言葉で弁論している本です。今この瞬間もどこかに潜んでいるであろう彼らに、弁護士、作家として本の一節を伝えるとしたら?
やはり「怪物になる必要はない」でしょうね。わたしたちは往々にして、自分自身を受けいれるために、現実に打ち克つ怪物にならねばならないと考えがちですから。自分自身として生きることがマイノリティーにとっては非常に難しいというのは事実で、それはいつも人を無力にさせます。怪物になって何もかもひっくり返してしまいたくなることも多いでしょう。どうすればいいのでしょうか? 正直、完璧な対策があるのかはわたしにもわかりません。でもまずは、ものを書き、踊ってみるようにと伝えたいです。この厳しい現実において、怪物にならずに自分を受けいれる方法は、書くことと踊ることの二つだと思うのです。自分の考えと自分の身体を守り、それらに形を与えて正当性を得る、そのきっかけになります。
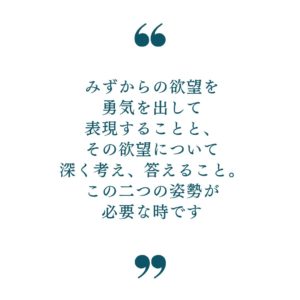
——新たに挑戦したい分野や扱ってみたいテーマ、あるいはこれまでの著書に関してもっと掘り下げて伝えたいことなど、これからの計画や目標についてお聞きしたいです。
先ほど「美しさ」が自分の重要なテーマの一つだとお話しました。最近、「踊る身体」の美しさとは何かについて、よく考えるんです。舞台公演、なかでも舞踊の歴史においては美しさの概念は少しずつ変わってきたのですが、その概念を覆したのはおもに、社会の外からやってきた「他者」でした。ヨーロッパ(パリ)で大きな人気を集めた東洋やロシアのダンサーたちのように。でも彼らは「ヨーロッパの人の目から見た美しさ」をダンスで表現することで認められていたに過ぎません。彼らがそれを拒み、本格的に「他者としての美しさ」を表現しはじめた途端、ヨーロッパの観客はそっぽを向きました。障害のあるダンサーたちのたどってきた歴史もそれと似ています。そういう内容の本を準備しているところです。関連文献を探したり、実際に舞台を経験して感じたことを記録したりしながら。
これからも、ものを書きながら、そしてダンスをしながら生きていくと思います。2022年8月末にドイツのデュッセルドルフで開かれた「Tanzmesse(タンツメッセ)」というダンスフェスティバルでは、「Becoming-dancer(ダンサーになる)」という作品を披露しました。ダンスと言語(文章)という二つの世界であとどのくらい生き残れるかわかりませんが、読者や観客のみなさんと長くお付き合いしていけることを願っています。わたしが幸いにも「怪物」にならずこうしていられるのは、読者や観客のみなさんがいらっしゃるからなので。
